この記事では、「四段活用」の見分け方と覚え方を徹底的に分かりやすく解説します。
四段活用の見分け方と動詞の活用
まず古文における動詞の意味、動詞の活用について説明したのち、四段活用の見分け方・覚え方について説明していきます。
古文における「動詞」とは?
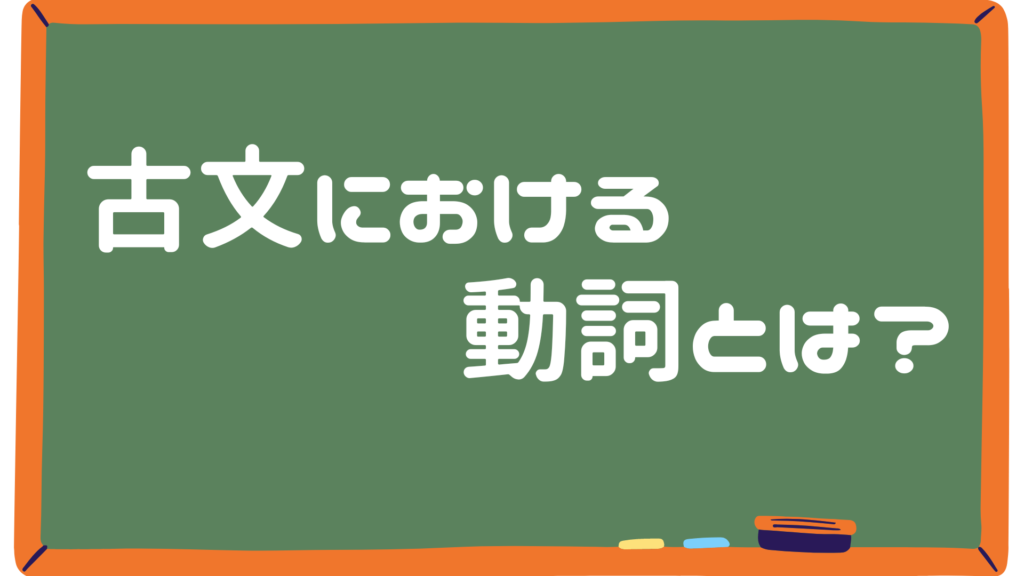
古文では、動作や存在を表す語で、「u」の音で終わるものを動詞と言います。例えば「行く」は「~く」で終わっているので動詞です。
活用ってなんだ?
動詞は活用する品詞です。活用とはある動詞の一部または全部が下に付く語によって変化することをいいます。
例えば「書く」という動詞は、いつも「書く」という形で出てくるわけではありませんよね?
「書く」に「ズ」を付けてみると「書く→書かズ」と変化します。
あるいは「書く」に「タリ」を付けてみると「書く→書きタリ」と変化しますね。
このように、下につく語によって形が変化することを活用といいます。
四段活用の見分け方・覚え方
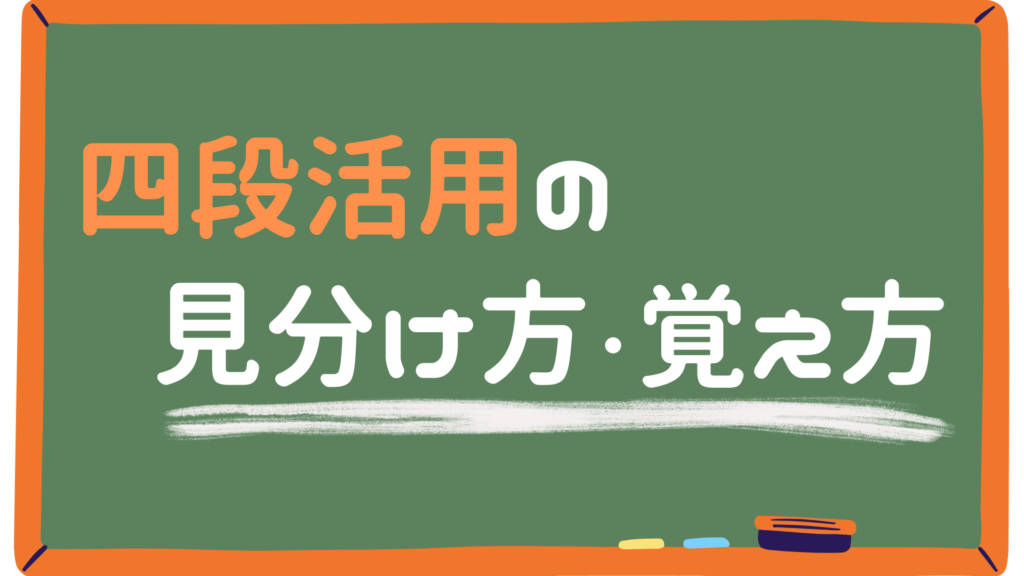
四段活用とは「a・i・u・u・e・e」のことです。
例えば、「書く」は四段活用なので以下のように活用します。
| 基本形 | 語幹 | 未然 | 連用 | 終止 | 連体 | 已然 | 命令 |
| 書く | 書 | か | き | く | く | け | け |
| – | – | a | i | u | u | e | e |
| 基本形 | 語幹 | 未然 | 連用 | 終止 | 連体 | 已然 | 命令 |
| 書く | 書 | か | き | く | く | け | け |
| – | – | a | i | u | u | e | e |
ちゃんと「a・i・u・u・e・e」になっていますね。
「か・き・く・く・け・け」とカ行になっているので、正確には「書く」はカ行四段活用です。
それぞれの活用形の意味は、以下のようになります。
- 未然形-まだ起こっていない形
- 例:書かず
- 連用形-用言(動詞など)に連なる形
- 例:書き取る
- 終止形-文が終わる形
- 例:書く。
- 連体形-体言(名詞)に連なる形
- 例:書く時
- 已然形-もうそうなっている形
- 例:書けども
- 命令形-命令するときの形
- 例:書け。
【補足】用言とは動詞・形容詞・形容動詞のこと!
見分け方
.png)
四段活用か他の活用かを判別するには、「-u」で終わっている動詞に「ず」を付ければいいだけです。
「ず」を付けたときに、「a」の音になる動詞は基本的に四段活用です。
例えば、「書く」なら「書か(a)ず」なので四段活用ですね。「行く」も「行か(a)ず」なので四段活用です。
「~できる」ではなく、「~しない」の意味で「ず」を付けます。
「~できる」の意味で「ず」を付けてしまうと、「書か(a)ず」とすべきところが「書け(e)ず」になってしまうからです。
必ず「~しない」の意味で、語尾に「ず」を付けます。
【例文】
ただ一人、笛吹きて、(宇治拾遺)
【現代語訳】
たった一人、笛を吹いて
【解説】
動詞「吹く」に「ず」を付けると、「吹か(a)ず」となるので、「吹き」はカ行四段活用の連用形です。なぜ「吹き」が連用形だと分かるかというと、「i」の音は「a・i・u・u・e・e」の2番目にしかないからです。
また、”カ行四段活用”というのは【活用の種類】で、”連用形”というのは【活用形】に該当します。
ですから、「吹き」の活用の種類は?と問われたら、カ行四段活用と答え、「吹き」の活用形は?と出題されたら、連用形と答えます。
一問一答で暗記しよう!四段活用の覚え方!
「+解答解説」ボタンを押すと「解説」と「答え」を確認することができます。
1.四段活用とは「a・●・●・●・●・●」と活用する動詞である。
2.「移す」の活用の種類は何か?
3.次の文章から四段活用の動詞を”そのままの形”で抜き出せ。
添ひて二、三町ばかり行けども(宇治拾遺)
四段活用の見分け方と覚え方のまとめ
- 四段活用:「a・i・u・u・e・e」
- 見分け方:「ず」を付けて「a」の音になれば四段活用

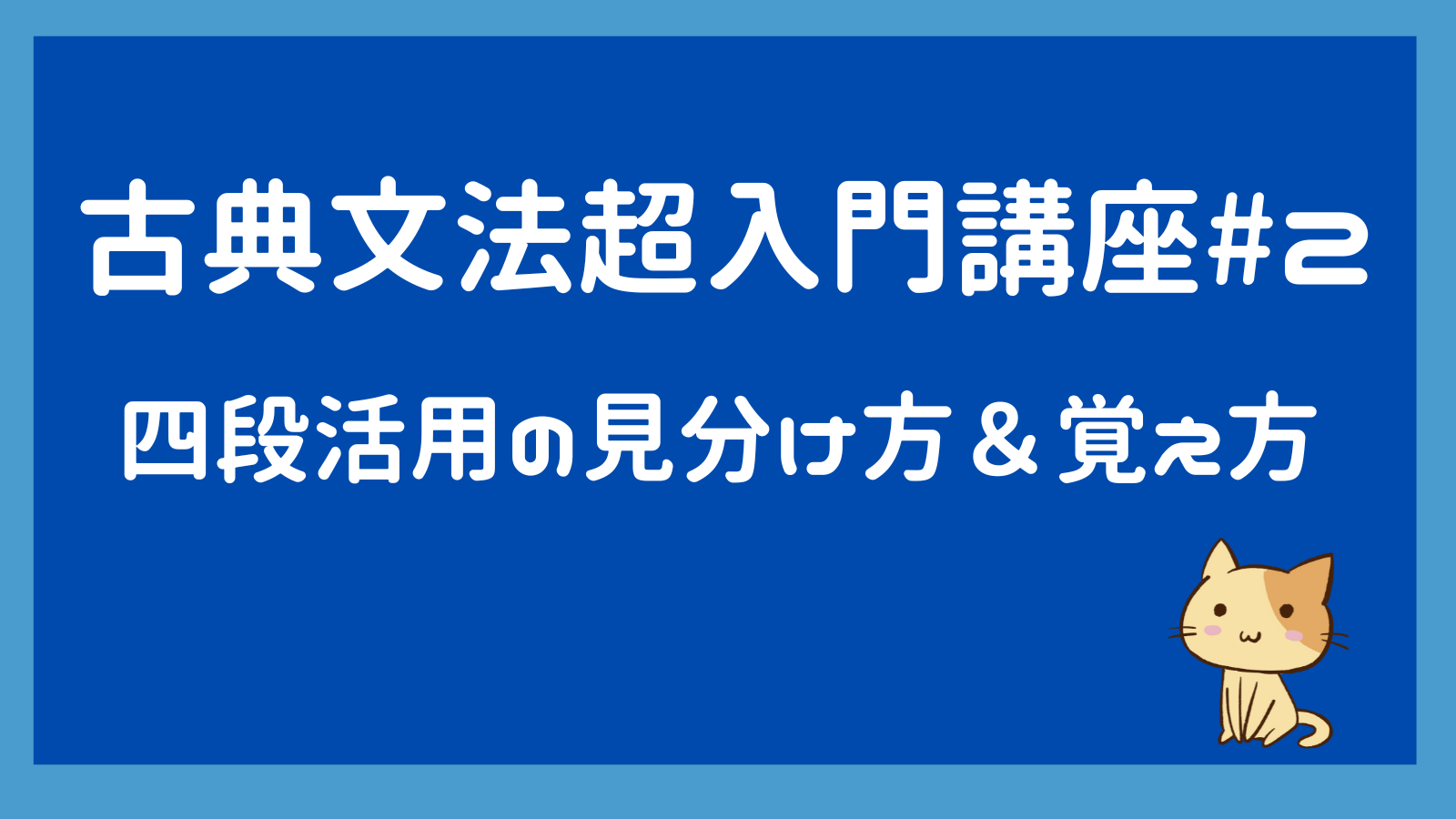
コメント