古典文法入門【第8講】の今回は、サ行変格活用(サ変動詞)について、わかりやすく解説していきます。
記事の最後には、充実の「一問一答」も付属していますので、覚え方も完璧です!
サ行変格活用(サ変)とは?

サ行変格活用の動詞は、「す(為)」「おはす」の2語のみです。
「す」の現代語訳は「~する」、「おはす」の現代語訳は「いらっしゃる」になります。
次の活用表を暗記すれば、基本的にはOKです。
| 基本形 | 語幹 | 未然 | 連用 | 終止 | 連体 | 已然 | 命令 |
| す | 〇 | せ | し | す | する | すれ | せよ |
| 基本形 | 語幹 | 未然 | 連用 | 終止 | 連体 | 已然 | 命令 |
| す | 〇 | せ | し | す | する | すれ | せよ |
【例文】
恋しき時の思ひ出にせむ(宇治拾遺)
【現代語訳】
恋しいときの思い出にしよう
【解説】
「せ」は「す」の未然形
ただし「す」については、「物語す(話す)」「愛す(かわいがる)」のように、複合語になる場合も多いです。
また「念ず(心の中で祈る)」のように、「ぜ・じ・ず・ずる・ずれ・ぜよ」の形になることもありますが、「~ず」となる場合でも「ザ行」ではなく「サ行」で処理します。
【例文】
そなたに向きてなむねんじ暮らし給ひける(枕草子)
【現代語訳】
そちらを向いて心の中で祈って、一日をお過ごしになった。
【解説】
「ねんじ」は「念ず」の連用形で、「サ行」変格活用です。「ザ行」ではない点に注意してください。
現代語でも「読書する」「勉強する」のように「~する」は複合語になりやすいですよね。
サ変動詞は「す」「おはす」の2語だけとはいえ、「~す」「~ず」の形になることも多いので注意が必要です。
サ変の複合動詞の見分け方

サ変動詞の複合動詞かを見分ける方法は3つあります。
次の3パターンは、基本的にサ変動詞だと思って大丈夫です!
サ行変格活用の複合動詞の見分け方
- 名詞+す
- 例:ものす(意味:いる・ある)
※漢字では「物す」
- 例:ものす(意味:いる・ある)
- 音読みの漢字1字+す
- 例:奏す(意味:天皇に申し上げる)
- 音読みの漢字1字+ず
- 例:案ず(意味:工夫する)
ただ最終的には、代表的なサ変動詞を覚えておくのが一番正確な判別法です。
幸いサ変動詞は数が少ないので、暗記で乗り切ることもできます。
主なサ行変格活用複合動詞一覧
- 啓す:「申す」
- 奏す:「天皇に申し上げる」
- 恋す:「恋をする」
- 愛す:「かわいがる」
- かなしうす:「かわいがる」
- 具す:「一緒に行く」
- 心す:「気を配る」
- ご覧ず:「ご覧になる」
- 念ず:「心の中で祈る」
- 打ず:「打ちたたく」
上記の代表的なサ変動詞の一覧は、古文単語力を高めるつもりで覚えてしまうと後が楽です。
1つ例文を確認してみましょう。
【例文】
見るに打ぜんこと、いとほしく覚えければ(宇治拾遺)
【現代語訳】
それを見るとむち打つことが、気の毒に思えたので
【解説】
「打ず」は主なサ変動詞の一覧にありました。ですので、一発でサ行変格活用と見分けることができますね。もちろん「音読みの漢字1文字+ず」はサ変!というルールでも見分けることが可能です。
続いて、一問一答で知識を定着させていきましょう!
一問一答でサ行変格活用を覚えよう!

一問一答集を何度も繰り返すことで、確実に文法事項を覚えることができます。
※それぞれの問題をタップ(クリック)すると、解答解説が表示されます。
【問題1】サ変動詞「す」を「未然・連用・終止・連体・已然・命令」に活用すると?
【解答】せ・し・す・する・すれ・せよ
【解説】
| 基本形 | 語幹 | 未然 | 連用 | 終止 | 連体 | 已然 | 命令 |
| す | 〇 | せ | し | す | する | すれ | せよ |
| 基本形 | 語幹 | 未然 | 連用 | 終止 | 連体 | 已然 | 命令 |
| す | 〇 | せ | し | す | する | すれ | せよ |
【問題2】次の《》内の動詞の”活用の種類”は何か?
旅の物語など《する》にぞ(御伽物語)
【解答】サ行変格活用
【現代語訳】
旅の話などをして
【解説】
「する」はサ行変格活用の連体形ですね。
【問題3】次の文中には3つのサ行変格活用の動詞が含まれている。全て”そのままの形”で取り出し、さらに”活用形”も述べよ。
男もすなる日記といふ物を、女もしてみんとてするなり。(土佐日記)
【解答】
す(終止形)
し(連用形)
する(連体形)
【現代語訳】
男もすると聞いている日記というものを、女もしてみようと思う。
【解説】
一文の中にサ変動詞の「す」が、「男もすなる日記といふ物を、女もしてみんとてするなり」と、3回登場していますね。
活用形は、それぞれ「す(終止形)」「し(連用形)」「する(連体形)」です。
このように「す」は「~する」という意味なので、サ変動詞は「す」「おはす」の2語のみとはいえ、古文読解で出会う頻度は高めです。しっかりと活用を暗記しておきましょう!
【問題4】次の中からサ行変格活用の「複合動詞」を”そのままの形”で取り出せ。
とかくするうちに、かの座頭、蜘蛛と現じて、我をまとひて天井へのぼり、ひたもの血を吸ひくらふ。(御伽物語)
【解答】現じ(サ行変格活用・連用形)
【現代語訳】
あれこれとするうちに、例の座頭は蜘蛛の姿を現して、私をまとって天井にのぼり、たっぷりと血を吸う。
【解説】
「現じ」はサ変の連用形で、「ぜ・じ・ず・ずる・ずれ・ぜよ」と活用する複合動詞です。意味は「現れる」です。
「現」が、「ゲン」と音読みの1文字の漢字であることから、「現じ」をサ行変格活用だと判別します。
「音読みの漢字1文字+ず」はサ変動詞でしたね。
まとめ:サ行変格活用のポイント
- サ行変格活用の動詞は「す(為)」「おはす」の2語のみ!
- サ変動詞の活用は「せ・し・す・する・すれ・せよ」!
- 「物語す(話す)」「念ず(心の中で祈る)」のような複合動詞もサ行変格活用!
以上で、サ変動詞の解説を終わりたいと思います。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます!

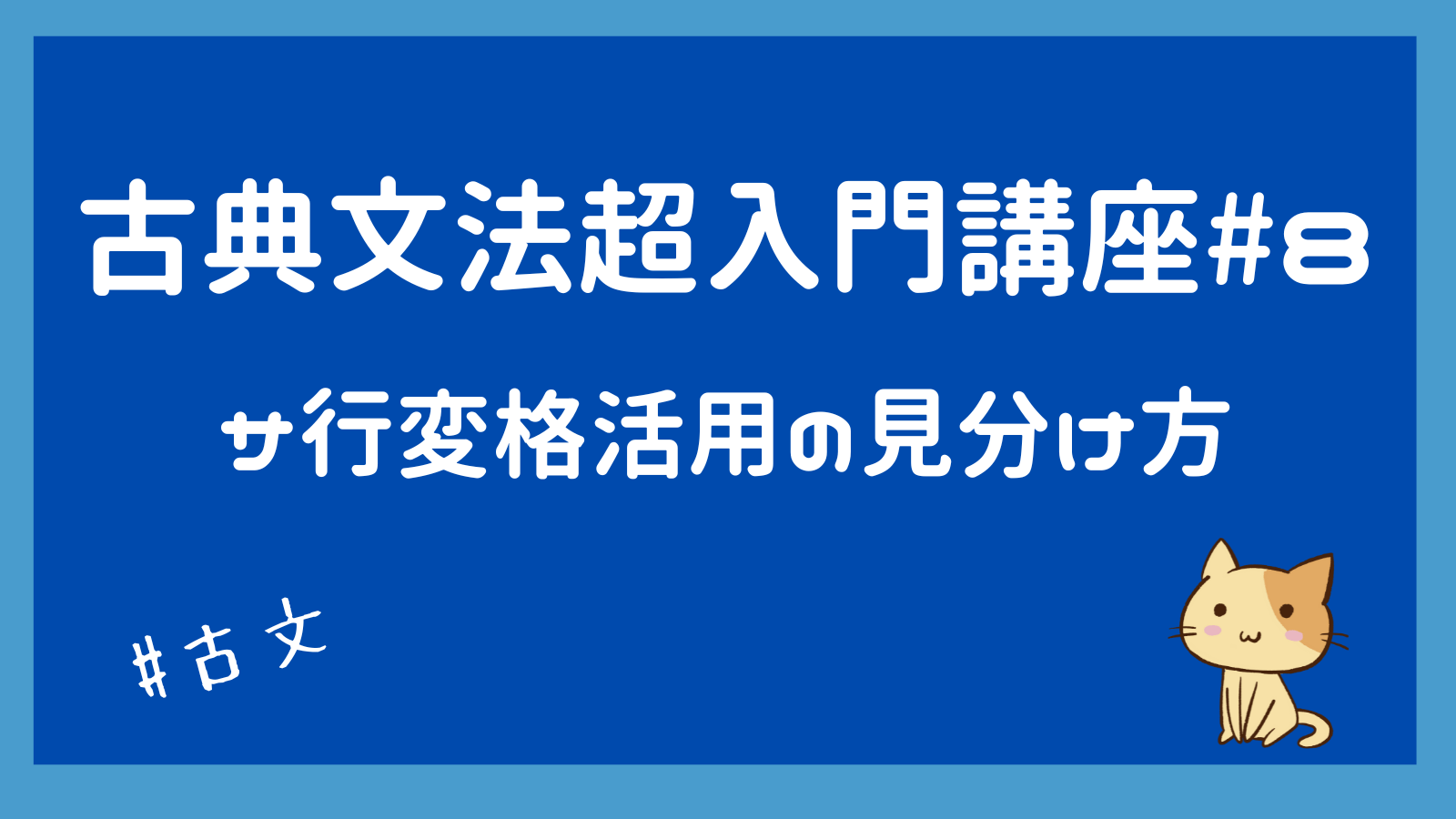
コメント