この記事では、『稲荷山古墳出土鉄剣銘』の内容を簡単にわかりやすく解説しています。
この記事を読めば『稲荷山古墳出土鉄剣銘』を完全理解できます!日本史の史料問題対策としてぜひご活用ください。
稲荷山古墳出土鉄剣銘の解説
『稲荷山古墳出土鉄剣』は埼玉県の稲荷山古墳から発掘された鉄製の刀で、この刀には乎獲居という人の自慢話のようなものが銘文として刻まれています。
この銘文を、『稲荷山古墳出土鉄剣銘』と言います。

そんな無名の人物の自慢話を、なんでありがたがっているの?
それは、この史料から以下の2つの大きな事実が明らかになったからです。
- 4~5世紀に、日本で漢字が使用されていたこと
- 5世紀のヤマト政権の勢力が関東まで及んでいたこと
弥生時代にはまだ文字がなく、古墳時代に入った4~5世紀の応神天皇の政権時に、王仁が文字を伝えたとされています。
その最古の証拠こそが、この『稲荷山古墳出土鉄剣』に刻まれた115文字の金石文です。
そして、この史料のもう一つの日本史的意義が、5世紀のヤマト政権の勢力が関東(埼玉県)にまで及んでいたことを明らかにしたことです。



つまり『稲荷山古墳出土鉄剣銘』から、5世紀のヤマト政権の勢力範囲と、「文字の使用」という2つの事実が分かるんだね!
ここからは、この鉄剣銘の本文を確認していきましょう。
この鉄剣の表と裏に、文字が書かれています。


「稲荷山古墳出土鉄剣」の表の文
〔表〕辛亥の年七月中記す。乎獲居臣、上祖の名は意富比垝…。
表の文で重要なのは「辛亥の年」だけです。西暦471年のことです。
剣道の練習で使う、竹でできた「竹刀」がありますよね。でも、今回の話は鉄剣です。
そこで西暦471年を、「竹刀(しない)じゃないよ、鉄剣だ」というゴロで覚えましょう!
つまり、5世紀後半には既に文字が使われていたのです。
また、稲荷山古墳出土鉄剣は埼玉県の稲荷山古墳から発掘されているため、5世紀のヤマト政権の勢力範囲が関東にまで及んでいたという事実も重要でした。
後半は乎獲居という無名の人物の自慢話なので無視してしまって大丈夫です。
続いて裏の文を見ていきましょう。
「稲荷山古墳出土鉄剣」の裏の文


〔裏〕…世々、杖刀人の首と為り、奉事し来り今に至る。獲加多支鹵大王の寺、斯鬼宮に在る時、吾、天下を佐治し、此の百錬の利刀を作らしめ、吾が奉事の根源を記す也り。
現代語訳代々大王の親衛隊長として朝廷に仕えてきた。ワカタケル大王の寺が斯鬼宮にあったとき、私は大王を補佐したので、この立派な刀にその由来を書き残すことにした。


やっぱり自慢話が書いてあるね。(笑)
どうやらこの乎獲居という人物は埼玉県の地方豪族で、ヤマト政権において大王の護衛隊長をしていたようです。
重要なのはここから!史料の本文中に出てくる「獲加多支鹵大王」とは雄略天皇のことなんです。
この人物は雄略天皇に仕えていたわけですから、ヤマト政権が関東にまで影響力を持っていたことが分かります。
また熊本県の江田船山古墳から出土した鉄刀にも「獲□□□鹵大王」という記述があります。
ところどころ欠けていますが、これも雄略天皇を表しているのです。
稲荷山古墳出土鉄剣銘に関する一問一答!


腕試し用に一問一答を2題設置しました。
問題をタップすると解答が表示されるので、ぜひ挑戦してみてください!
【問題1】『稲荷山古墳出土鉄剣銘』に記載のある「辛亥の年」とは西暦何年か?
【解答】正解は471年です。
「竹刀(しない)じゃないよ、鉄剣だ」というゴロで覚えるんでしたね。
【問題2】ワカタケルの大王とは( )天皇のことである。
【解答】正解は雄略天皇です。
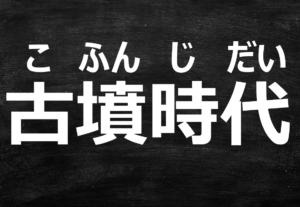
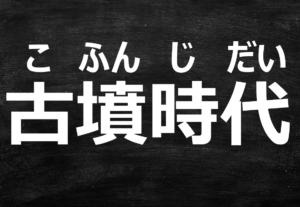

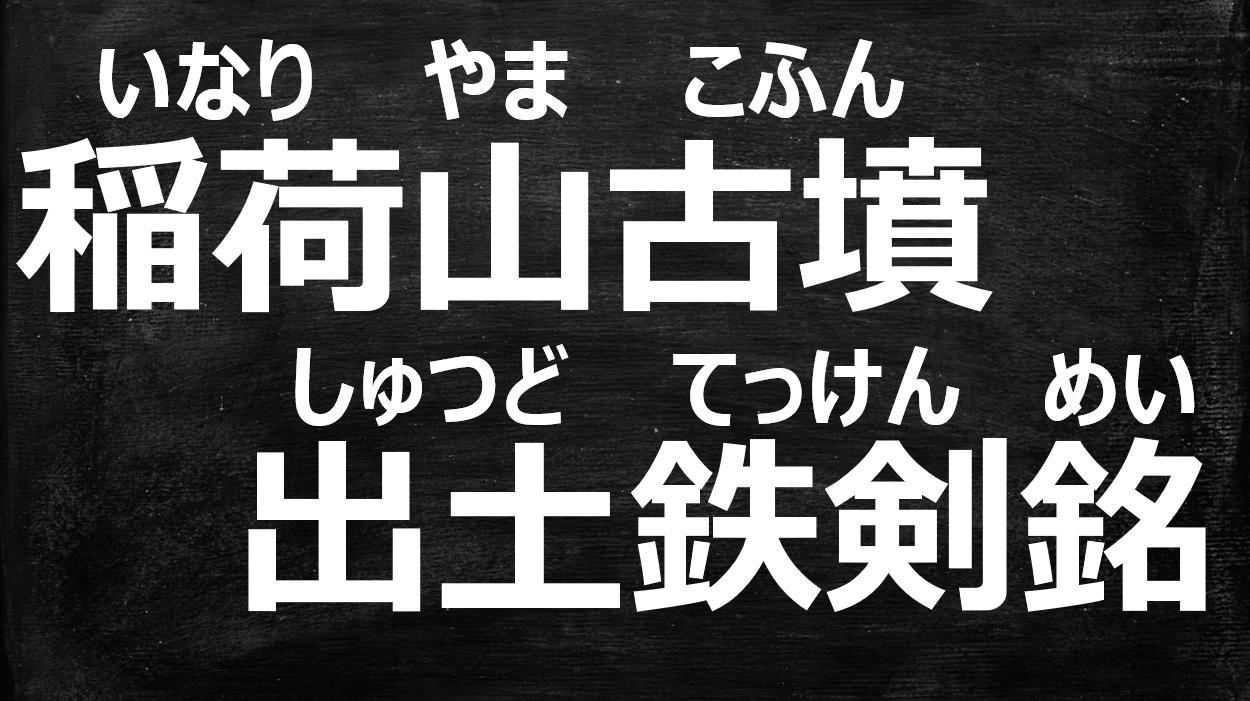
コメント